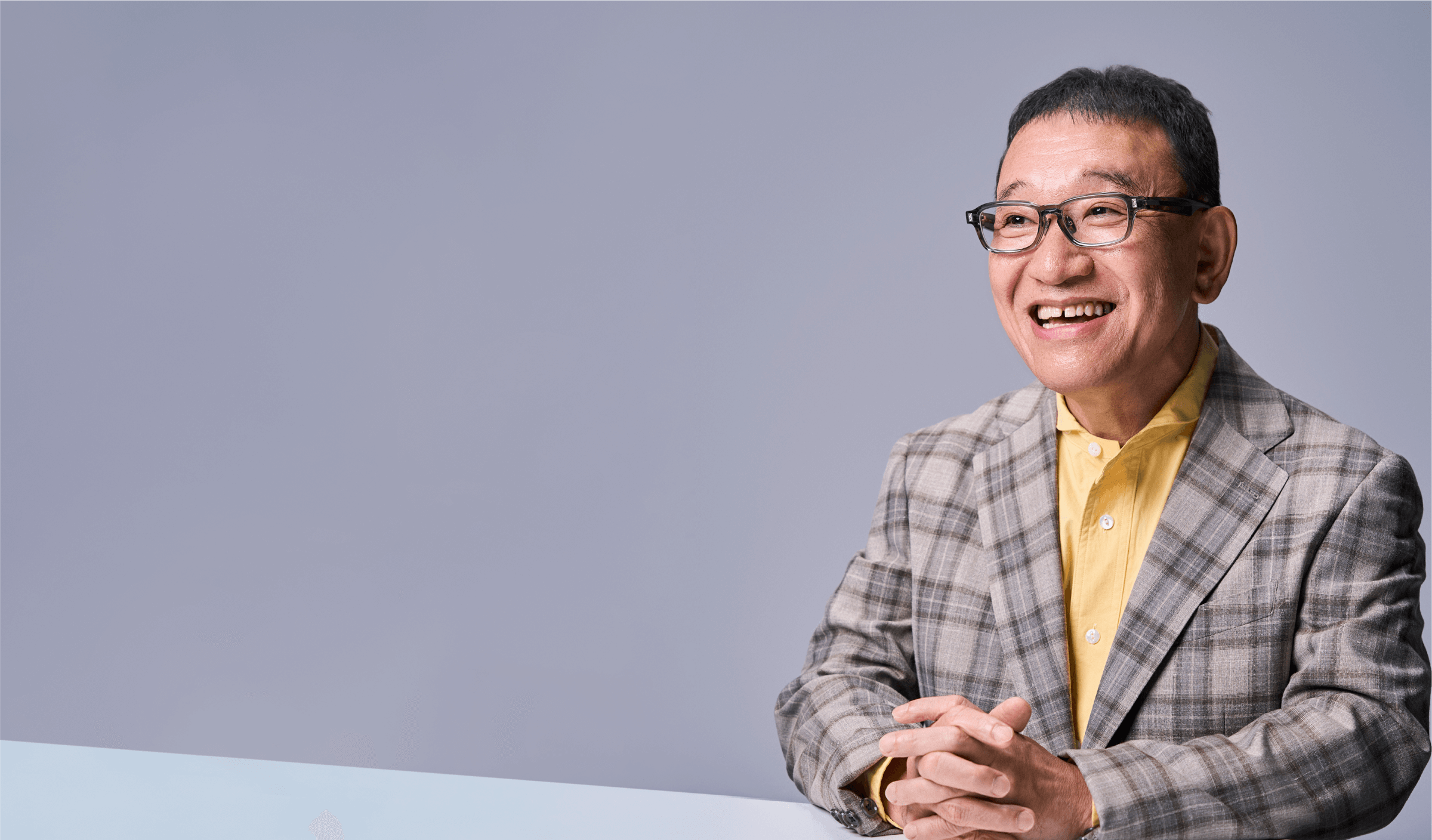
Top
Interview
社長挨拶
設立当初から変わらない経営理念
「会社は働く人のためにある」
—1986年に設立したブライセン(設立時の社名は株式会社エイ・アイソフトウェアズ)。当時はどんな思いで立ち上げたのでしょうか?
最初に作ったのは「会社は働く人のためにある」という経営理念でした。お客さまや株主の方たちももちろん大事ですが、最も重要なのは「会社で働く人」である。そういう思いを持った数名の仲間が集まって作った会社がブライセンです。
—どんな事業を展開していこうと考えたのでしょうか?
当時はまだITが一般化しておらず、どちらかというとニッチなビジネスでした。マーケットも小さくITでできることも限られていたので、「ITでこんなことを成し遂げよう」といった野望はなかったけれど、「世界で戦える技術者を目指す」という目標がありました。
—1991年に社名を「株式会社ブライセン」に変更しましたが、名前の由来は?
西村寿行先生の「無頼船シリーズ」を由来としています。さまざまな過去をもつ荒くれ男たちが船に乗って社会の悪と闘うお話で、スーパーエリートでもない、ダメなところもたくさんある人間が協力することによって何かを成し遂げる姿に共感しましたし、世界を舞台にしているところも自分の理想と重なりました。
—40周年も目前ですが、設立からこれまでを振り返って会社にとっての大きな変革期はありましたか?
会社も私もすごく運が良かったので、これまでは運の流れに身を任せてきたような状態でした。ところが39期の上期に業績が悪化し、「これまでのような運任せではなく、中長期的なビジネス戦略を立てる必要がある」と思い知らされる状況になりまして……ただ、業績は悪化したものの、「会社自体は良い方向に向かっている」という実感が私のなかにはありましたし、実際に40期の上期には黒字に転じることができました。
—具体的にはどんなことをしたのでしょうか?
直近だけでなく、3か月先、半年先、1年先といった中長期のビジネス展開について、私自身も各部署に介入しながら細かい戦略を立てていくようになりました。経営検討会議では2期先の方針を作っていくなど、「数年先に向かって今は何をやるべきか」という視点で分析や戦略を立てられるような会社になってきた実感があります。

一貫して模索し続けてきたのは 「困っている人のために自分たちができること」
—中長期的な戦略とは?
これまではブライセンジャパンがあって、ベトナム、ミャンマー、韓国、カンボジアといった拠点が点在していましたが、今後はそれらの拠点を一体化した経営を強化していく必要があります。グループ間のコミュニケーションを増やし、全体をより身近に捉えることによって新たなビジネスを創出するなど、グループシナジーを高めながら企業としての付加価値も高めていく。それは各拠点間だけでなく、各事業部間でも同様です。
—実際に効果が出ているところなどはありますか?
5つある事業部のシナジーが高まってきていると感じます。例えばクラウド型倉庫管理システム「COOOLa®」を利用いただいているお客さまに、需要予測型クラウド自動発注システム「B-Luck」をご紹介したりと、ブライセンジャパンのなかでの情報共有やコラボレーションは現在かなり確立されてきています。
各部署が互いに「何をやっているのか・何が必要なのか・何が足りないのか」といったことを共有し補い合う関係性が生まれ、会社に新たな付加価値をもたらしていることを実感します。
—中長期的な戦略として、そういった各部署間・各拠点間のシナジー向上のほかに考えていることはありますか?
プロモーションの強化ですね。これまでは「あまり目立ちたくない」という思いが私自身にあったので積極的にプロモーションを行なってこなかったのですが、ブライセンが次の段階に進むためにも、受け身ではなく自ら発信していくことも重要だと今は考えています。
—逆にこれまでプロモーションをせずにやってきたのが驚きです。
基本的にブライセンは人間関係を重視しているので、お金儲けのための無理な付き合いみたいなものがないんです。「良い人間関係」で繋がってきたご縁でこれまでやってきたというのが正直なところです。
例えば、いまや会社の軸のひとつとなっているオフショア事業ですが、元々はベトナムの養護施設に寄付をしていたところから始まっていて……身寄りがない子どもがきちんとした職につけるように、日本に呼んで専門学校でエンジニアの仕事を学んでもらったんです。ただ、そうやってITについて学んでも現地にはソフトウェア会社がない時代でしたから、「じゃあ現地に会社を作って、仕事を提供したらいいじゃないか」と2009年にスタートしたのがブライセンベトナムでした。
最初は4人から始まった小さな会社ですが、2018年には200人規模にまで拡大して単年度黒字を達成するほどの大きな会社になりました。養護施設に寄付をしていた当時は「将来的にベトナムに進出する」なんて考えていなかったので私自身も驚いていますが、まさに「良い人間関係」で繋がってきたご縁から生まれたビジネスでした。
—「良い人間関係」とはどんなところから生まれるのでしょうか?
「困っている人がいたら助ける」というのは当然のことですが、ベトナムやミャンマー、カンボジアでも常にその思いがビジネスよりも先にありました。それは海外だけの話ではなく、私たちが日本で作っているサービスや製品についても同様です。
お客さまと勉強会を開いて困っていることをうかがったり、エンドユーザーに困っていることを直接聞いて解決策を考える。そうやって新しいビジネスやプロダクトが生まれてくることもあります。大手企業の傘下に入らず、「困っている人のために自分たちができること」を独自のやり方で模索し続けてきたブライセンだからこそ、本当に必要とされているものを作ることができる。ブライセンの強みであり、責務でもあると思っています。

ブライセンの企業風土とは?
根幹にあるのは「正義」
—ところで、ブライセンはどんな企業風土をお持ちでしょうか?
「正義」に尽きます。最近はあまり言わなくなりましたが、かつて私は「人を動かすのは役職ではない」ということを社員に常に伝えていました。仕事というのは、お互いがしっかりと納得し合ってやっていくものであって、「正しいか、正しくないか」という判断基準を必ず入れるようにしています。そのうえでどうしても権限をもつ役職が必要になりますが、基本的には「納得し合って仕事を進めていく」という風土がブライセンにはあります。
—そういった会社の理念をどのような場で社員の方たちに伝えているのでしょうか?
入社式や会社方針説明会、社員旅行、新年会、バーベキューなど、自由参加のものを含めるとほぼ毎月なんらかでコミュニケーションをとる場があります。そういった意味で、私は圧倒的な権力を持っているわけではなく、「社員の近くにいる社長」だと思っています。
—ブライセンへの就職を検討している人に対して「こんな人がブライセンに向いている」とアドバイスするなら?
「人のために何かをやりたい人」がいいかもしれません。私たちが何かをしないかぎり、私たちに何かをやってくれる人なんて絶対にいませんから、「何をしてもらえるか」ではなく「自分たちには何ができるか」を考えられる人であってほしいですね。
ブライセンには「困っている人に対して、自分たちには何ができるか」を考えて行動に移せる人が集まっていると私は思っています。
ブライセン代表 藤木の活動
ブライセン代表 藤木の出演メディア

CRC NEWS
1994年に発足したイギリス・ロンドンの本拠から、カナダ・トロントに主要局を移行し、独自ジャーナリズムを規範とした英国放送事業系の報道メディア。
日本国内だけに留まっていたワンランク上の経済情報をグローバルに拡散していくコンテンツサイト。

社長名鑑
社長と繋がる社長"直結"メディア
国際チームで生み出したITソリューションで
多くの課題を解決!“つながり”を大切に挑戦を続ける社長の目指す未来とは

GLOCAL.
グローバルな視点でローカルビジネスを行なっている人や企業、モノコトを紹介するインタビューメディア
グローバル連携で、
ITビジネスの未来を拓く

PRESIDENT STATION / Sound of Oasis
TOKYO FM 系列ミュージックバード局
“明日を語らう対談番組”GOOD PERSON~
新春スペシャル!
sound of oasis×プレジデント・ステーション



